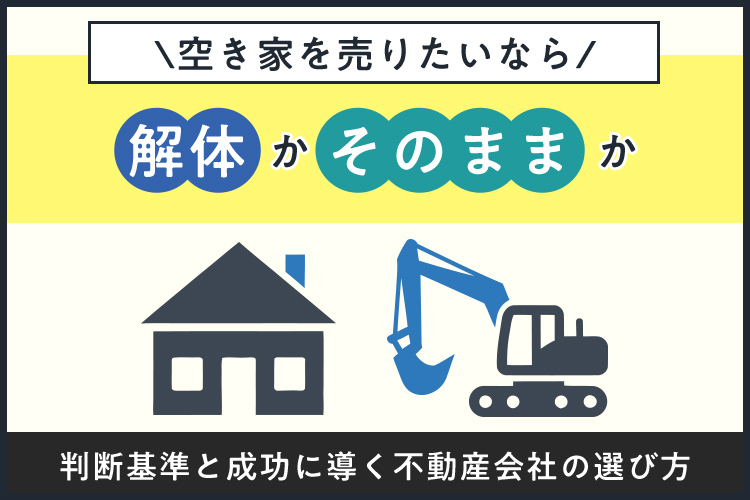2025/09/02(火)
空き家所有者必見!特定空家指定基準の解説と注意点

空き家の所有を検討されている方、あるいは既に所有されている方にとって、空き家問題は深刻な課題です。
放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があり、所有者自身にも多大な負担がかかります。
特に、特定空家と指定されると、固定資産税の増額など、経済的な負担が一気に増大します。
そこで今回は、特定空家と判定される基準について、具体的な事例を交えながら解説します。
目次
特定空家の指定基準
倒壊の危険性
特定空家と判定される最も大きな要因の一つに、倒壊の危険性があります。
具体的には、建物の老朽化による構造体の損傷、基礎の不同沈下、柱や梁の腐朽、屋根や外壁の剥離・破損などが挙げられます。
例えば、基礎に大きな亀裂が入っていたり、柱が傾いていたり、屋根材が剥がれ落ちそうになっている状態などは、倒壊の危険性が高いと判断される可能性があります。
これらの状態は、目視で確認できる場合もありますが、専門家による調査が必要となるケースもあります。
衛生被害の危険性
放置された空き家では、ゴミや汚物の蓄積、害虫や害獣の繁殖などによる衛生被害の危険性も高まります。
例えば、家の中にゴミが散乱していたり、悪臭を放っていたり、ネズミやゴキブリなどの害虫が大量発生している状態などは、衛生被害の危険性が高いと判断されます。
これらは、近隣住民の健康にも悪影響を及ぼすため、早急な対策が求められます。
景観の損壊
適切な管理が行われていない空き家は、景観を損なう可能性があります。
例えば、建物が放置されたまま老朽化し、外壁が剥がれたり、窓ガラスが割れたり、雑草が繁茂したりする状態は、景観を著しく損なうと判断される場合があります。
また、地域の景観計画やルールに適合しない状態も、景観の損壊に該当する可能性があります。
その他危険性
倒壊、衛生被害、景観損壊以外にも、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態が特定空家と判定される場合があります。
例えば、隣家の敷地にはみ出した樹木の枝が通行の妨げになっている、動物の糞尿による悪臭が発生している、不審者の侵入によって防犯上の問題が生じているなど、近隣住民の生活に支障をきたす状態が該当します。

空き家と特定空家の違い
空き家の定義
空き家とは、原則として居住や利用がされていない住宅を指します。
ただし、所有者の事情や状況によっては、一時的に居住や利用されていない状態でも、空き家とはみなされない場合があります。
特定空家の定義
特定空家とは、空き家のうち、上記の4つの基準(倒壊の危険性、衛生被害の危険性、景観の損壊、その他危険性)のいずれかに該当するものを指します。
これらの基準は、周辺住民の安全や生活環境の保全という観点から設定されています。
指定基準との関係
特定空家と判定されるためには、上記の4つの基準のいずれかに該当する必要があります。
複数の基準に該当する場合もあります。
各基準の判断は、建物の状況、周辺環境、危険性の程度などを総合的に考慮して行われます。
固定資産税増額
特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税額が大幅に増加する可能性があります。
具体的には、更地状態と同等の税額となる場合もあり、経済的な負担が非常に大きくなります。
まとめ
特定空家は、倒壊の危険性、衛生被害の危険性、景観の損壊、その他周辺の生活環境への悪影響といった基準に基づき指定されます。
空き家であっても、これらの基準に該当しなければ特定空家とはなりません。
しかし、特定空家に指定されると、固定資産税の増額など、大きな経済的負担を強いられることになります。
そのため、空き家の所有者は、これらの基準を理解し、適切な管理を行うことが重要です。
放置すると、多大な損失を被る可能性があることを認識しておきましょう。